高次脳機能障害者と家族の心情からみる「中途障害」の難しさ

今回は、中途障害としての高次脳機能障害の、患者と家族の困難さを言語聴覚士の視点から書いていきます。
高次脳機能障害は、多くが脳の疾患や頭部外傷から生じる中途障害です。
健康な日々から急に障害者となることで、これまでのアイデンティティーが崩れ、将来の計画は白紙に。
この変化に戸惑い、
「どうしていったらいいのかわからない」(混乱)、
「私は何も変わっていない」(否認)、
「生きていても仕方がない」(落ち込み)、
または病気や事故に対して、復帰できない社会に対し
「なんで自分だけがこんな目にあうのか納得できない」という怒りや恨みの感情などが入り混じります。
この状況で、これからの人生に希望を見出せなくなってしまう人は非常に多いのです。
家族にとっても、ある日をさかいに別人になったかのような人を、夫、妻、子供として受け入れる難しさがあります。
さらに「障害者の家族」となったことで、介護に時間を取られ、友人との話題も変わり、これまでの付き合いが途絶えがちになってしまいます。
このように家族自身の生活も大きく変わります。
本人と家族は、障害を受け入れつつ、その人らしい人生の実現や生き方について模索する余裕がありません。
同時に、再発したら、悪化したら、今後の生活はどうなるのかという不安もつきまといます。でも、考えたくないのが本人と家族の心情だと思います。
医療従事者は、一緒に課題に立ち向かり、患者とその家族が障害を受け入れ、医療情報をわかりやすく伝え、将来の見通しについて冷静に説明する必要があります。

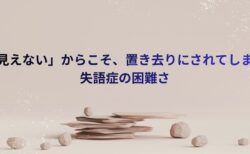



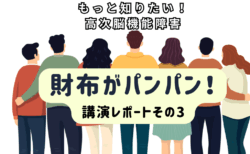



LEAVE A REPLY