発想の転換がオンライン言語リハビリ実施におけるKeyだった!

みなさん、こんにちは。言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語リハを始めました。対面とオンライン、何が違うの?ということについて話していこうと思います。
「そんなので言語リハなんてできるわけない」と言われた頃
私がオンライン言語リハビリテーションのアイデアを思いついたのは、コロナ禍のずっと前のことでした。当時、オンライン自体が一般的ではなく、私がこの構想を話すと、多くの人から「そんなので言語のリハビリなんかできるわけない」と言われたものです。
私自身も、「対面で行っていることを、そのままオンラインでやったらどうなるだろう」という発想しかなかったのです。そこで、まずは10名の失語症者にモニターになって頂き、研究を始めてみました。しかし、研究を進めていく中で、この考え方こそが大きな落とし穴だったことに気づくことになります。
みんなが陥る「対面の再現」という罠
コロナ禍になり、否応なしにオンラインで言語リハに取り組む言語聴覚士の方々の発表や取り組みを見る機会がありました。当初の私と同じく、ほとんどの方が病院で実施していたものと同じアプローチを取っていたのです。つまり、「対面でやったことを、なんとか自宅でやろうとする」という方法です。
例えば
- 絵カードをプリントアウトして自宅に郵送する。それを並べてもらってポインティングの課題をする。
- 文字チップを郵送して、絵カードにあわせて並べてもらう
- 書き取り課題をして、書いたものを画面に見せてもらう
- ドリル課題をプリントアウトして、オンラインで正誤の確認をする
など、対面で必ずやっている課題です。
オンラインの限界が見えた瞬間
しかし、実際にやってみると、この方法の限界がすぐに見えてきました。
カード選択の課題では、患者さんがどのように手元を動かしているのか、迷っている様子や選択のプロセスが全く分からないのです。対面なら、患者さんの表情や手の動き、迷いの過程まで観察できますが、オンラインではそれが不可能でした。
書字の課題も同様です。どのように字を書いているのか、運筆の様子が全く観察できません。結果として書かれた文字は見えても、書く過程での困難さや特徴的な動きは把握できないのです。
当然の結論「オンラインはやっぱり無理」
このような経験を重ねれば、「オンラインはやっぱり無理だよね」という結論に至るのは当然でした。対面と同じ方法を使い続ける限り、オンラインは常に「劣化版」「代替手段」という位置づけから抜け出せないのです。
発想の転換:「オンラインなら何ができるのか」
この限界にぶつかった時、私は重要なことに気づきました。
「対面と同じことをオンラインでやろうとするから無理なのではないか?」 「オンラインなら、何ができるのかを考えてみよう」
この発想の転換が、すべての始まりでした。オンラインを対面の代替手段として捉えるのではなく、オンライン独自の可能性を探ることにしたのです。
次回は、この発想の転換によって見えてきた、オンライン言語リハビリテーションの独自性と可能性について詳しくお話しします。




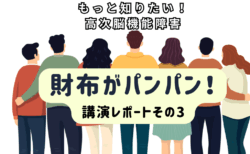



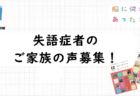
LEAVE A REPLY