失語症の方の生活の困り事 ~制度のはざま~言語聴覚士のお仕事
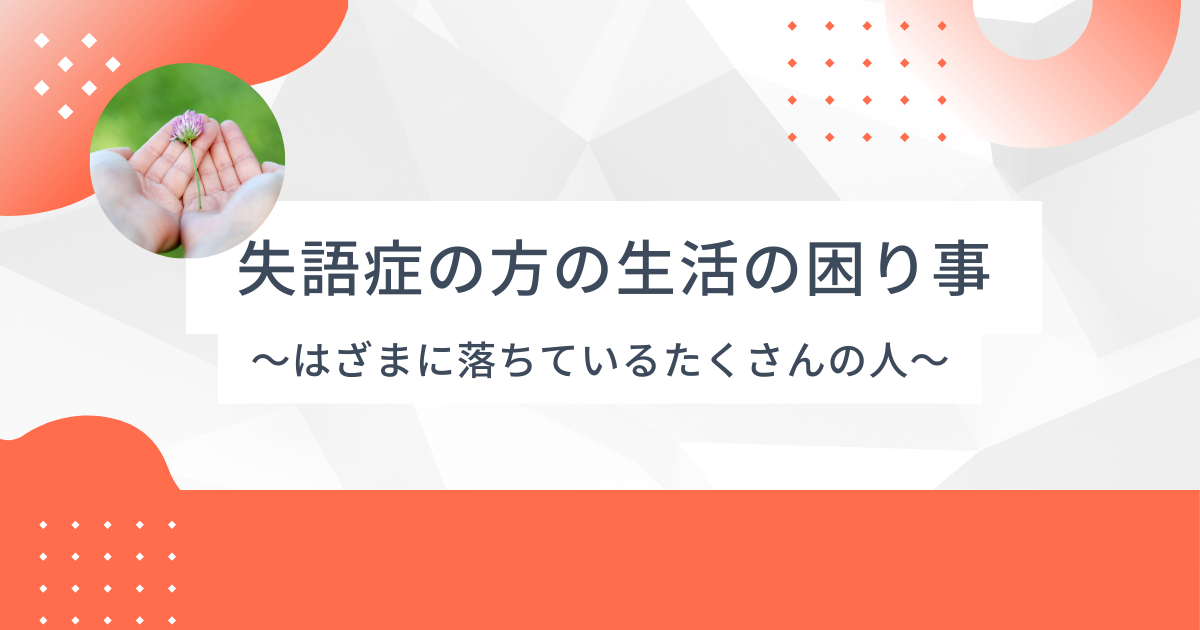
こんにちは、言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語療法を行っています。
前回は失語症の方が抱える「不全感」という心理的課題についてお話ししました。今回は、失語症の方が日常生活で直面する具体的な困り事について、お伝えします。
アンケート調査で見えてきた現実
NPO法人失語症協議会という団体が、失語症の方とご家族にアンケート調査を行いました。そこで浮かび上がってきた困り事は、私たちが想像する以上に深刻で、かつ具体的なものでした。
身の回りのことは自分でできる失語症の方でも、様々な場面で困難を感じているという現実があります。
移動・交通機関での困り事
バス・電車・タクシーの利用
バスや電車は利用できたとしても、タクシーが難しい。理由は、タクシーでは行き先を伝えなければならないからです。
また、電車であっても、遅延等のアナウンスが聞き取れない場合があります。そのため、本人も、ご家族も何かがあったら・・と、不安になります。麻痺のために電車やバスが使えないのではなく、失語症のためにバスや電車の使用を控えているのです。
これは身体的な問題ではなく、コミュニケーションの問題が移動の自由を奪っているという深刻な課題です。
医療機関での困り事
医師とのコミュニケーション
病院に行って医師とのやりとりが難しいという問題も深刻です。具体的には:
- 医療用語が入っている会話は理解しにくい
- 医師からの質問に答えられない
- 医師や薬剤師からの注意事項を聞き取れない
- その場では理解したつもりでも、一部を忘れてしまう
これらの理由で、一人で病院に行けないという状況が生まれています。通院は、健康管理に関するので誰にとっても重要。ですが、失語症の方にとっては家族の同伴が必須となってしまうのが現状です。
公的手続きでの困り事
市役所などでの手続き
市役所などでの手続きも非常に難しいものです。これは普通の人でも複雑に感じることがありますが、失語症の方にとってはさらに困難です。そうしたところに家族の手がかかってしまうということが困り事として挙げられていました。行政手続きのデジタル化が進んでいますが、失語症の方にとっては必ずしも解決策になっていないのが現状です。
解決に向けた取り組み
意思疎通支援事業の開始
こうした失語症の方とご家族の困り事を解決するために、「失語症者のための意思疎通支援事業」という事業が始まりました。
この事業は、失語症の方が社会参加する際のコミュニケーション支援を目的としており、全国的に広がりつつあります。
社会全体で考えるべき課題
これらの困り事を見ると、失語症は単なる個人の医学的問題ではなく、社会参加を阻む社会的な問題でもあることが分かります。
私がオンライン言語療法を始めた理由の一つも、これらの日常的な困り事を少しでも軽減したいと思ったからです。自宅でトレーニングができれば、通院の負担も減りますし、継続的な改善も期待できます。
まとめ
失語症の方が直面する困り事は、私たちの想像以上に多岐にわたり、日常生活のあらゆる場面に及んでいます。
しかし、適切な支援とトレーニングによって、これらの困難は軽減できるものです。社会全体の理解と、個人の継続的な努力の両方が必要ですが、確実に改善の道はあります。
これで知識・理論シリーズは完了です。次回からは、具体的なトレーニング方法について詳しくお話ししていきます。理論を理解した上でのトレーニングは、より効果的になるはずです。




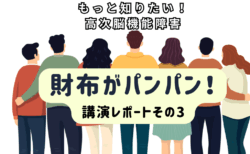


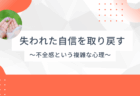
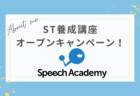
LEAVE A REPLY