「言葉が出ない」悩みと向き合う – 脳科学が教えてくれること
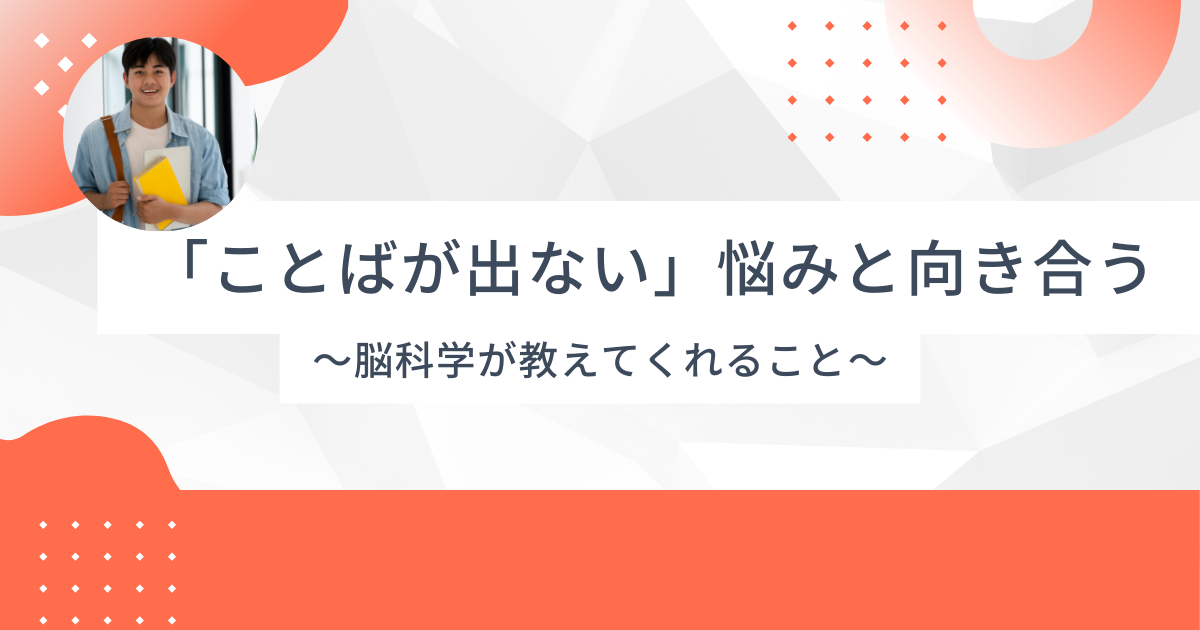
こんにちは、言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語療法を行っています。
前回は雑談の本質と、「聞く」ことの大切さについてお話ししました。今回は、「言葉が出ない」という悩みの背景にある脳のメカニズムについて、詳しく解説したいと思います。
言葉が出ない悩みは、失語症だけの問題ではない
言葉が出ないという悩みは、失語症の方だけではありません。病気や障害と関係なく、うまく言葉が出ないと悩んでいる人は少なくありません。
ただし、失語症の方は脳を損傷した既往があるので、いわゆる口下手とは違います。また、病気や怪我をする前はもっと話ができていたわけですから、「世の中には口下手の人もいますよ」と言われても、それで納得はできませんよね。
脳の構造から理解する「言葉が出ない」理由
言葉が出ないという状況が強く現れるのは、心理的に不安、不満、不信がある場合や、緊張が強い状況です。これは脳の機能からも説明ができます。
脳の3つの層構造
脳には、脳幹、旧皮質、新皮質という3つの層があります。
- 脳幹や旧皮質:原始的な脳で、生存に必要な機能や感情を司っています
- 新皮質:最も新しく進化した脳で、言葉や思考といった高度な機能を担っています
基盤が揺れると上位の脳は機能しない
重要なのは、原始的な脳が基盤となって、その上に新しい脳が乗っかっているということです。
建物と同じで、基盤が揺れると、その上位の脳は機能しなくなります。つまり、不安や恐怖で原始的な脳が揺らぐと、新皮質の働きは低下してしまうのです。
これは当たり前の現象です
不安や不満、緊張状態で言葉が出ないということは、多くの人が経験上分かっていると思います。しかし、脳の機能から考えると、これは当たり前のことなのです。
疲れているときや眠たいときに言葉が出にくくなるのも、同じ理由です。生存を優先するため、不快な状況では言葉はより出にくくなるものなのです。
対処法:脳の仕組みを理解した実践的アプローチ
これは失語症の方に限らず、誰にでも起こる自然な反応です。このことを理解した上で、緊張する場面では以下のような対処法が効果的です:
- 深呼吸をする
- 事前にリハーサルをする
- 準備をしておく
原始的な脳を落ち着かせることで、新皮質がより良く働き、言葉も出やすくなるのです。
まとめ
「言葉が出ない」という悩みは、脳の構造から考えると自然な現象です。自分を責める必要はありません。大切なのは、この仕組みを理解し、適切な準備と対処法を身につけることです。
失語症の方も、そうでない方も、脳の基本的な仕組みは同じです。不安や緊張をコントロールすることで、言葉へのアクセスは確実に改善していきます。
次回は、失語症の方が抱える深い心理的課題「不全感」について、そしてそれとどう向き合っていけばよいのかをお話しします。

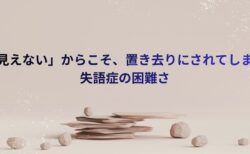



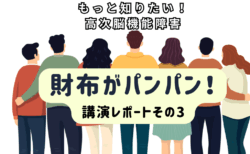

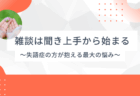
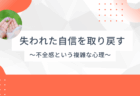
LEAVE A REPLY