注意機能が障害された人の生活は・・

前回は注意機能の4つの分類、「持続」「分配」「転換」「選択」についてお伝えしました。
では、こうした注意機能が障害されるとどうなるかについて、分類別に書いてみました。
例えば. . .
- 本を読んでる先から集中力が途切れてしまう。
- 一つのことしか見えてない
- 同時に何かができない (例えばご飯を食べてるけど、テレビに気を取られたらもう手が止まってしまう)
- 人の話を聞いているときに、別のことに気を取られてしまうと、相手に話が耳にはいってこない
- ちょっとのことで気が散ってしまう
- 周囲の情報が、すべて同じ分量で頭に入ってきてしまう
- 必要に応じて、注意をふりわけることが難しくなる
- 何かに取り掛かったらそればかりで「注意がはがせない」、途中でやめられない
乱暴にまとめてしまえば、相手の話に集中できないと記憶にも残らない(記憶に影響)、作業効率がめちゃくちゃ悪くなるし(遂行機能に影響)。情報処理に追われて頭が疲れる。疲れたから「休憩しよう」と、注意を切り替えることもできない。疲れたからミスが増えるし、イライラする(情緒にも影響)このように多方面に影響が出てしまうのです。
注意機能は、本人も相手も気がつきにくい、わかりにくいものですが、様々な困難さのベースにあると考えおくとよいと思います。




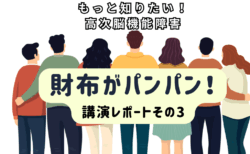




LEAVE A REPLY