コミュニケーション支援で最も大切なこと:「話したい・伝えたい」気持ちを育てる

こんにちは。言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語リハを提供しています。当初は成人を対象としていたのですが、2022年頃から小児の相談が増えてきました。先日はよくある音の置換、例えば、「キがチになる」などについて、そして日常生活の中での誤りについて書きました。本日は、最も大事な「話したい気持ち」「伝えたい気持ち」について書いていきます。
技術より大切な「気持ち」の育成
コミュニケーションに課題があるお子さんへの支援において、背景を評価することは大切ですし、課題へのアプローチも重要です。しかし、絶対に見落としてはいけないのは、その子が「話したい・伝えたい」という気持ちを育てていくということなんですよね。
そこをきちんと育ててあげないと、だんだん年齢が上がるにつれ、自身の課題に気がついたり、周囲とうまくいかないことに気がつき始めたときに話さないお子さんになってしまいますよね。
思春期以降に見られる変化
「幼少期には明るい子だった」という思春期以降の方はたくさんいます。
小さい頃は屈託なく話していたのに、成長と共に自分の話し方や伝わりにくさに気づき、次第に口数が少なくなってしまう。このような経過をたどるケースを、私たちはよく目にします。
年齢が上がると自己認識が高まり、他者との比較もできるようになります。その時に「自分は話すのが下手だ」「どうせ伝わらない」という気持ちが先に立ってしまうと、せっかくの支援も効果を発揮しにくくなってしまいます。
どんなに適切でも「気持ち」がなければ
どんなに適切な評価をして、プログラムを組んでも、本人がお友達や他人と話したいという気持ちがなくなってしまうと元も子もないと思うんですよね。
技術的なスキルの向上と、コミュニケーションへの意欲。この両輪がバランスよく育っていかないと、真の意味でのコミュニケーション能力の向上にはつながりません。
支援の最も大事なこと
支援の最も大事なことは、「話したい・伝えたい」という気持ちと成功体験の積み重ねだと思います。
成功体験の積み重ね
「これこれができない」ではなく「こうしたらできた」を伝えることが大事です。
お子さんが「伝わった!」「分かってもらえた!」という体験を重ねることで、コミュニケーションそのものへの肯定的な気持ちが育っていきます。小さな成功でも、お子さんにとっては大きな自信となります。
長期的な視点での支援
私たちが目指すべきは、単に発音がきれいになることや語彙が増えることではありません。そのお子さんが将来にわたって、人とのつながりを大切にし、自分から積極的にコミュニケーションを取ろうとする気持ちを持ち続けられることです。
支援者として心がけたいこと
技術的な完璧さを追求するあまり、お子さんの「話したい」気持ちを萎縮させてしまっては本末転倒です。
評価や訓練の精度を高めることももちろん大切ですが、それ以上に:
- お子さんの「伝えたい」という気持ちを受け止める
- 小さな成功を一緒に喜ぶ
- できないことよりも、できたことに注目する
- コミュニケーションの楽しさを実感してもらう
これらのことを日々の支援の中で大切にしていきたいと思います。
お子さんが生涯にわたって豊かなコミュニケーションを築いていけるよう、技術と気持ちの両面から支援していくことが、私たち言語聴覚士の役割かと思っています。

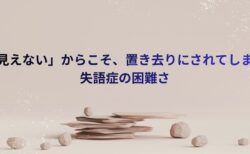



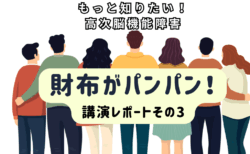

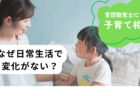

LEAVE A REPLY