リハビリテーションが目指すもの~上田敏先生の講演より~言語聴覚士というお仕事

昨日は、そもそもリハビリテーションって何か?について書きました。今日は、リハビリテーションが目指すものは何かについて書きます。
ゴールは機能回復だけでは不十分
病気やケガで歩けなくなった人が、訓練をして、歩けるようになっただけではゴールではありません。反対に、歩けるようにならなかった、車いすが必要、つえが必要であっても、目標未達成とは必ずしも言えません。なぜなら、リハビリテーションとは
「活動向上に支えられた参加の向上を目指す」ものだからです。
訓練をして歩けるようになる(これが活動向上)が目標でなく、例えば、歩けるようになって当事者会に出かける、知人とランチに行く(これが参加の向上)が目標です。
杖が必要であっても、車いすであっても、介助を必要としても、外出したり、通勤できれば目標達成です。
いつまで絵カード使うの??
言語聴覚士として、すごく、すごく残念なことの一つが、失語症の人に、いつまでもいつまでも、絵カードを見せてその名前を言わせるという訓練(呼称と言います)をしている話を聞くことです。ネットで検索しても、絵カードを見せているイラストや写真がたくさん出てきます。これが必要な時期もあるのですが、、、、ずっとそれだけ??って思いませんか?
英語の勉強を考えてみてください。いつまでも、名前を言うだけの勉強なんてしないですよね?コミュニケーションの場に参加するを目標として、今、何をすべきか、どうしたら参加できるのか、そんなことを考えて言語聴覚士としてのかかわりを考えていきたいと思います。
日常会話ができればOK??
同じく残念なのが「もう話せるので大丈夫」と安易にリハビリを終了してしまう話。軽度の人のリハビリがとてもないがしろになっている話をよく聞きます。
言語聴覚士と1対1で、それも静かな言語室で話せるとしても、それがいかに特殊な環境かわかりますよね。日常生活は、周囲に雑音も多いし、複数との会話がふつうではないでしょうか。同じく、ある程度、状況がわかってしまう家族と、それなりに日常会話ができたら治ったでもないです。私たちは、自分の事をあまり知らない他人と、コミュニケーションを重ねていくのだから。どこまでを「回復した」というのかは、医療者が決めることではなく、本人や家族と一緒に考えるものだと思っています。
さいごに・・4月25日を失語症の日にプロジェクトしています!ぜひお読みください




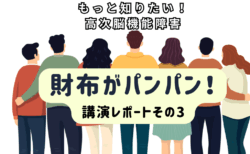




LEAVE A REPLY