口から食べるを支えるNo1〜言語聴覚士のお仕事〜

医療と健康、そしてリハビリの情報〜言語聴覚士というお仕事〜本日もよろしくお願いします。先日、「口から食べる」ことをキーワードに、地域コミュニティーを発足されたこちらの歯科医師の先生の会に参加してきました。なかなか熱い場で、問題提起やいろいろな症例の紹介、そして、笑いありの楽しい時間でした。
あさ出版 (2015-04-14)
売り上げランキング: 151,901
食事って、栄養補給だけが目的ではない!
とても印象に残ったこちらの話
食卓を囲むのは、生物の中でほとんど人間だけです。動物のほとんどは奪い合い。食事の「事」というのは、心や作法、気持ちが入ったものでとても大切な営みだと思うのです。
肺炎のリスクがあるから絶食!と、安易に決めつけないでほしいという願いはこちらにも書きました。「一口でも食べること」に最後までこだわって、そして、本人が望むのであれば「好きなものをなるべく安全に食べさせる」ことの意味を考えながらお仕事をしている人はたくさんいます。そんな思いで、訪問診療されている先生からは、たくさんの「再び食べることができた」症例が報告されました。
あなたは、人生の最期をどうしたいですか?
ただし、ここで、「安全基準」というジレンマがあります。昔、聞いた言葉が「医師の利益と患者の利益は相反する」つまり、リスクを抱えても食べたい患者さんと、疾患を治療して状態が安定してほしい医師との利益は一致しにくいものです。
たとえ寿命が短くなっても食べたいものを食べたいのか??そして、本当に死を意識する時に「このまま何もせずに自然に死にたい」と思うのかどうか?これは、本人しかわからないものです。さらに、ここで家族の意向も関与してきます。
医療とは、「本人のための医療であり、家族のためではない」
日本ではまだまだ「本人の意思」が尊重されているとは言い難いです。そもそも意思表示ができる時期に、表明しているケースは稀で、さらにその意思に沿ったケアプランや治療方針が立てられることも少ないからです。
- こちら、ACPアドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning)の説明です。患者さんの意思決定が低下する前に、あらかじめ、プランを立てて、その人の思いに沿うケアプランです。少しずつ導入され始めている地域や病院があるそうです。私は始めて知りました。
- こちら、聖路加病院の「リビングウイル」どのように最期を迎えたいか、具体的な選択肢が書かれており、イメージがつきにくい一般の方でも使い易いものです。
日本では「縁起でもないと」と言われかねませんが、避けては通れないことですので、真摯に考えたいと思います。
こちら、過去記事です。「食べること」への思いを書いたものです。





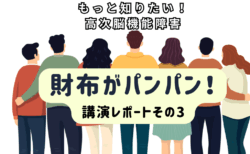




LEAVE A REPLY