なぜ日常生活で、音の間違いが続くの?

こんにちは。言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語リハを提供しています。当初は成人を対象としていたのですが、2022年頃から小児の相談が増えてきました。先日はよくある音の置換、例えば、「キがチになる」などについて書きましたが、今日は、セラピー中ではできるようになっても、日常生活であまり変わりが見られない段階のお子さんについて書いていきます。
セラピー中と日常生活でのギャップ
「セラピーの時ではきれいに発音できるようになったのに、家や学校ではまだ音の間違いがある」—このようなお子さんのケースをよく経験します。なぜこのようなギャップが生まれるのでしょうか。
メタ認知の発達と自己モニタリング
話すことへの集中が妨げる気づき
一つ目の要因は、まだメタ認知が育っていないお子さんの場合、自分の発話に意識が向きにくいことです。「言い間違えたな」「ここは修正しないといけないな」ということを話しながら気づくことが難しいのです。
話すことに夢中になっていて、自分の発話に注意が向かない。そうするとこれまで通りの話し方をしてしまうので、音の誤りが出現することがあります。
発達年齢による制約
これは発達年齢にもよりますが、10歳以上にならないと難しく、発達の遅れがあるお子さんでしたら12歳、13歳でもなかなか難しい時があります。しかし、そこが育ってくると改善は見られてきます。
相手の反応から学ぶ力
もう一つの気づきのきっかけは、相手が「え?」という顔をしたりしたときに「僕の言い方が間違えたんだな」と気がつくことです。つまり、自分の発話のモニタリングはできていなくても、相手の表情を見て発話の間違いに気がつくという場合もあります。
これもやはりある程度発達年齢が上がらないと難しいですし、特に相手の表情に注意が向きにくい自閉傾向のお子さんでは難しいところもあります。ただし、相手が聞き返したら「こういう風に言い直すんだ」ということを知っておき、対処ができると良いかと思います。
日常生活での関わり方の重要性
過度な修正は逆効果
最後に重要なのは、あまり発話をきれいにすることにこだわりすぎて、日常生活で指摘ばかりするとお子さんがしゃべらなくなってしまうということです。
せっかく「相手に伝えたい」という気持ちがたくさんあるお子さんであれば、きれいに発話することよりも、まずその気持ちを受け止めることが大切です。
効果的なフィードバックの方法
いちいち修正するのではなくて、「ここもあれ、ちょっと聞きにくかったかなぁ」というような意識化を促すような質問を時々投げかけるだけでいいと思います。そして本人が言い直した時は「よくわかったよ」というようなプラスのフィードバックをしてください。
支援の本質を問う重要な視点
ある先生がおっしゃっていた言葉があります。
「きれいに発音できるけれどあまり話そうとしないお子さんと、音はある程度不明瞭なところもあるけれどもたくさんお話をするお子さんと、どちらに育てたいですか?」
この言葉は、とても示唆に富んでいると思っています。
私たち支援者は、技術的な完璧さを追求するあまり、お子さんの「伝えたい」という気持ちや「話す楽しさ」を奪ってしまっていないか、常に問い直す必要があるのではないでしょうか。
日常生活での応用を考える時、発達段階に応じた現実的な目標設定と、お子さんの意欲を大切にした関わり方のバランスが重要だと感じています。

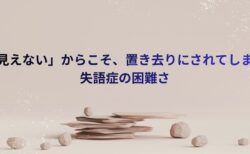



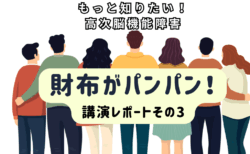

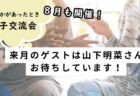

LEAVE A REPLY