食べたくない本人と、食べさせたい介助者~嚥下障害者の意思決定支援No2~

さて、食べたくない人の問題があります。認知症、特にレビー小体型認知症の人とかでしたら、幻視、違うものが見えたりしますね。周囲からしたらあり得なけれども、本人の中はお茶碗のご飯の中に虫が見えるとか、おかずの中にわけわからないものが見える、本人にはそれが見える、だから嫌だって、それは当然です。他にも、毒が入っているとかよく聞きます。介助する側からすると、それはあり得ないから、食べてちょうだいって思いますよね。
アルツハイマー型認知症の方は、嗅覚障害になり、味覚も低下するので、何を食べているのかわからない、味がしない、それも砂を噛んでいる状況かも知れません。
そもそも、空腹感がなくて、要らないと言う人もいます。
他に、高齢者になると、生活リズムがバラバラになってる人います。特にずっと長い間で一人暮らしをしてる方は、3食定期的に食べている人はほとんどいません。しかし、病院、施設に入ると、3食出ますね、身体がついていかないのです。でも、介助者は、朝ごはんでも8割食べてほしいですね。摂取量を確保したいから「たべて、たべて」と一生懸命なのです。仕事だし、本人のために栄養つけさせようと食べさせてるんだけども、実はこれっていいのか、本人にとって何が一番いいんだろうって、モヤモヤを抱えてお仕事をしてると思うんです。
食べたくない、特に食べることが本人にとって、非常にストレスになる場合、食べないと命の安全に関わるけれども、無理やり食べさせるのはどうなのか?と多くの人は思いながら、限られた時間の中で介助をしているのが現実です。




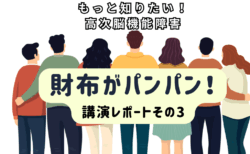




LEAVE A REPLY