子どもの音の間違い:「キ」が言えないのではなく「キとチの違いが曖昧」という視点
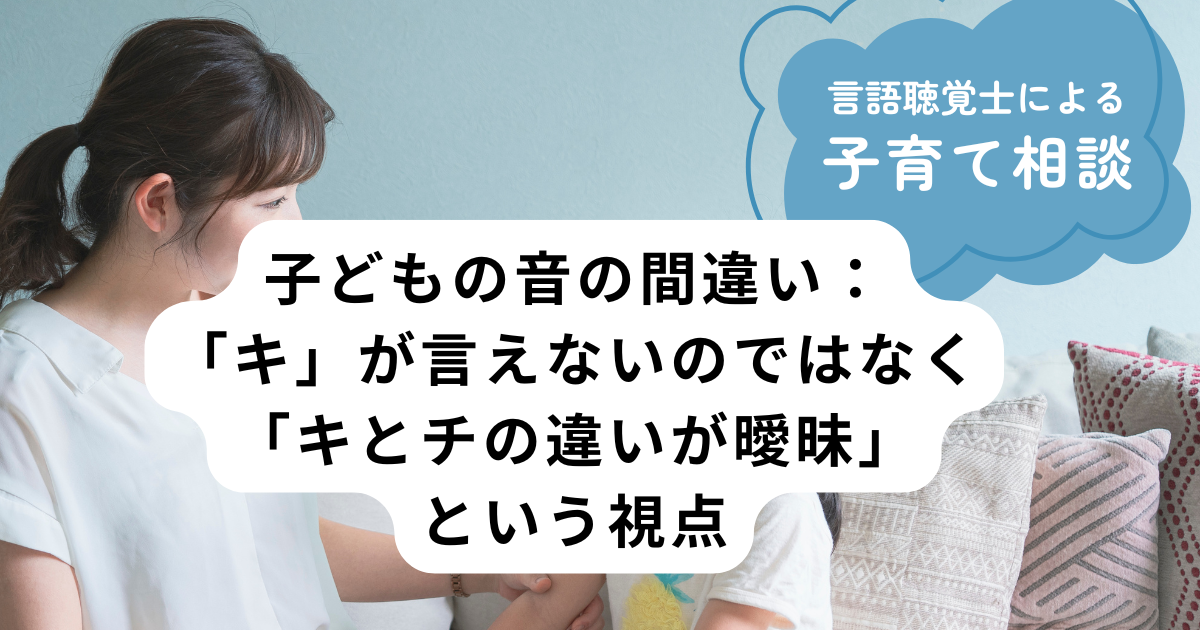
こんにちは。言語聴覚士の多田紀子です。2019年からオンラインで言語リハを提供しています。当初は成人を対象としていたのですが、3年前から小児の相談が増えてきました。本日はよくある音の置換、例えば、「キがチになる」などについて書きます。
よくある音の置換現象
子どもの言語発達において、「き→ち」の音の置換はよく見られる現象です。例えば、大樹くんのことを「大地くん」と呼んでしまうといったケースです。
こうした音の間違いを見ると、多くの場合「キが言えない」という構音の問題として捉えがちですが、実はもっと根本的な問題が隠れていることがあります。
入力段階での問題を見逃していませんか?
実際には、「キ」と「チ」の音韻的な違いが曖昧で、聞き取り(入力)の段階から間違えている場合も多くあります。入力が間違っていたり不明瞭だったりすれば、発音が間違うのは当然の結果です。
同様に、書き間違いをするお子さんも、そもそも入力の段階で間違って認識していることがあります。
具体的な例で考えてみましょう
「ポップコーンって書いてみて」と言って、お子さんが「コップコーン」と書いたとします。そこで絵を見せて「これは何かな?」と聞くと、「コップコーン」と答える。
お子さん本人は「コップコーン」だと思っているので、当然「コ」を書きます。これは構音の問題ではなく、音韻認識の問題なのです。
段階的なアプローチの重要性
このようなお子さんには、まず以下の段階を踏む必要があります:
1. 音韻弁別の確立
「2つの音が違うんだよ」ということをまず認識してもらう必要があります。この気づきがなければ、言い間違いや書き間違いは減りません。
2. 自己モニタリング能力の育成
自分の発音の違いにも気づかないといけません。「キチキチと言ってみて」と言うと「キチチチ」のようになれば、「音どうかな?」と気づきを促します。
3. 従来の構音指導の限界
「キが言えない」のではなく「キとチの違いが曖昧」なお子さんに、「キはこうやって音を出すんだよ」とだけ伝えても、間違いがなくなるのは難しいのです。
新しい視点での支援を
音の間違いを単純な構音問題として捉えるのではなく、音韻認識や聞き取りの段階から総合的に支援することで、より効果的な言語発達支援が可能になります。
お子さんが自分の音の違いに気づき、正しい音韻認識を身につけられるよう、段階的で包括的なアプローチを心がけていきたいと思います。




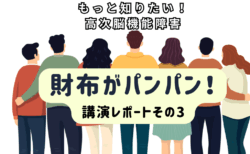


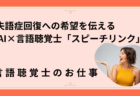
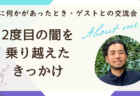
LEAVE A REPLY