講演会レポート② 高次脳機能障害の症状と生活での困難

前回に続き、兵庫県加東市での講演会レポートです。今回は「症状と生活上の困難」についてご紹介します。
高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害には、行政が定義した分類は大きく4つ。注意障害・記憶障害・遂行機能障害・社会的行動障害です。
-
注意障害:気が散りやすい。複数のことを同時に処理しにくい。不要な情報を取捨選択しにくい。
-
記憶障害:病気の前のことが思い出せない。新しいことが覚えられない。作業中に忘れてしまう。
-
遂行機能障害:計画を立てる、順序立てて行動することが難しい。優先順位や段取りが難しい。
- 社会的行動障害:怒りっぽい。自主性が乏しい。やる気が起きない。
*このように「できない」を羅列すると、当事者の方は傷つくかもしれませんが、わかりやすく敢えて
この表現にしています。
こんなことが難しい
私たちの脳は、とても怠けものなのです。慣れたことはすぐに省エネモードに切り替えます。みなさんも、経験ありますよね?はじめは緊張してくたくたになったものも、慣れてしまえば「息をすって吐くように」楽になっているってことが。この「息を吸って吐くように」楽になったことが、脳を損傷した人にとって難しくなるのです。例えば
- メモを取る
- その日の予定を立てる
- 冷蔵庫の中のものをみて、ざっと献立を決める
- お買い得商品を見て、予定していた献立を変更する
- 緊急でない仕事は後回しにする
こうした省エネモードのことに、いちいちつまずいてしまうのが、この障害の大変なところです。
誤解されやすい
これらの症状は「怠けている」「性格の問題」と誤解されやすく、人間関係に大きな影響を与えることがあります。「本人は精一杯なのに、分かってもらえない」という悩みはよく耳にします。
また、講演では「家族が直面する困難」についても触れました。たとえば、伝えたことが伝わらない、約束を守れない、感情のコントロールが難しい…。支援する家族自身が疲れてしまうケースも少なくありません。ただ、こうしたことがなぜ生じるのか、障害について知ると、少しだけ楽になる方も少なくありません。
参加者の皆さんが熱心にメモを取ってくださる姿から、このテーマへの関心の高さを改めて感じました。次回は、当日いただいた質問とその回答を中心にご紹介します。

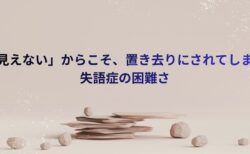



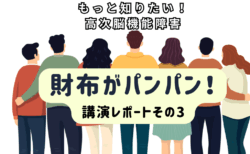


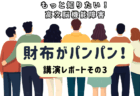
LEAVE A REPLY